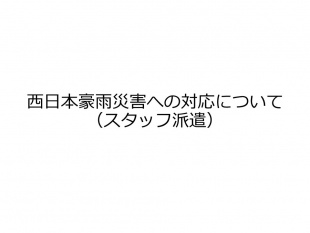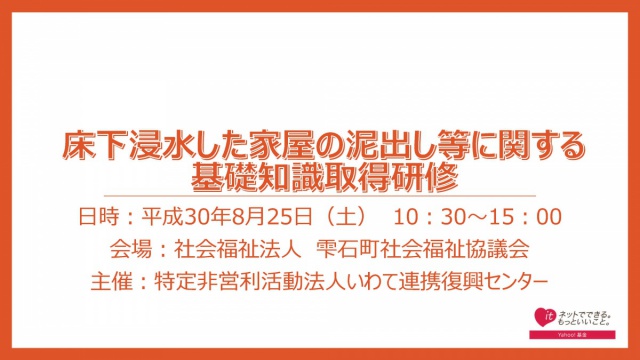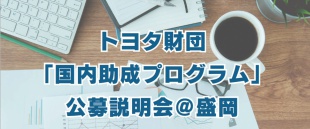| 名称 |
2018年度 花王・みんなの森づくり活動助成
|
|---|---|
| 内容 |
身近な緑を守り育てる活動、身近な緑の大切さを次世代に伝える活動に要する費用を助成します。
<応募資格>
身近な緑を守り育てる活動、身近な緑の大切さを次世代に伝える活動に取組んでいる団体
・任意の市民団体、NPO、町内会・自治会、学校などを 対象とします。
・公共団体や営利を目的とした団体は対象に含みません。
・指定管理業務を担っているNPOの場合、指定管理業務の内容は助成申請できません。
|
| 助成金額 |
森づくり活動と環境教育活動に要する費用を対象として、
1・2年目各50万円、3年目25万円を上限に助成
15~20 団体を採択予定
|
| 募集期間 |
2018年8月1日~2018年10月14日 ※当日消印有効
|
| お問合せ先 |
公益財団法人 都市緑化機構
|
| URL | https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2018_boshu |
復興庁様主催のアイディアソンのご案内です。
[Fw:東北Weekly vol.13]親子で楽しむ福島の伝統工芸文化
~福島からの伝統工芸の未来をみんなで考えよう
関連地域:福島県全域
【地域課題】
福島県では、シルクや木綿製品、木工製品、風土玩具など、高品質で多彩な工芸品をもとに、ファミリー層の需要に応える、時代に即したユニークで新しい製品づくりにも挑戦の意欲を持っている人々がいます。しかし、全国規模での認知獲得はまだ途上にあり、使い手の声を反映した斬新な製品やその活用方法の提案が必要です。
【企画趣旨】
日常生活から離れた存在となりつつある福島の高品質な伝統工芸品が、子どもやファミリー層にとって身近な存在になるにはどのような課題があるのでしょうか。今回のFw:東北Weeklyでは、子育て世代のていねいな暮らし楽しむアイテムとしての伝統工芸品を、大人の目線と子供の目線で考えていきます。
▼日時:2018年8月23日(木)10:15-11:45(開場 10:00)
▼会場:チルドリンカフェ本部@日本橋室町
(東京都中央区日本橋室町1-6-13 2F)
※アクセス https://goo.gl/maps/u1GkJwqjnsq
※銀座線「三越前」駅(A1出口)より徒歩1分、(A2出口・エスカレータあり)より徒歩1分
※東西線「日本橋」駅(C1出口)より徒歩5分
※浅草線「日本橋」駅より徒歩5分
※JR「新日本橋」駅より徒歩7分、「東京」駅(日本橋口)より徒歩10分
※東京駅からは「無料巡回バスメトロリンク日本橋」東京駅八重洲口のバス停をご利用ください。
▼定員:30名
▼参加費:無料
▼参加申込:下記URLよりお申し込みください。
【URL】https://goo.gl/eKMJe3
▼登壇者 ※順不同/敬称略
櫻田武(公益財団法人福島県観光物産交流協会 観光物産館 館長)
福島県福島市瀬上町出身。東京で長らく(22年間勤務)福島県産品に携わる仕事に従事。百貨店の福島県物産展担当、福島県初の首都圏アンテナショップ「ふくしま市場」での勤務、日本橋ふくしま館「MIDETTE(ミデッテ)」の立ち上げなどを通じ、首都圏での福島県産品の販路拡大や観光客誘致へのアピールに尽力。2017年より福島県観光物産館に勤務。2018年より館長を務める。
蒲生美智代(NPO法人チルドリン 代表理事)
NPO法人チルドリンは、全国2万人のWEB会員をもち、1回に約2000名の集客を実現する「ママまつり」という地域ママの自主イベントをサポートし年間30回を主催する。活動は「食を育む、エネルギーを選択する、レジリエンス(防災)で集う、仕事に就く、ICTを活用する、森と共創する」と社会問題に拡がっている。ママたちが考える社会課題を、暮らしの中で楽しく学ぶことからはじめる活動を全国展開している。
▼プログラム(予定)
10:15 開会メッセージ
10:20 クロストーク「福島の伝統工芸のある子育て」
ゲスト: 櫻田 武氏
ゲスト: 蒲生 美智代氏
ホスト: 原亮
10:35 ミニアイデアソン
11:30 LIKEorJOIN/コミットメントカード記入
11:40 Fw:東北活動紹介/閉会メッセージ
▼参加対象者:
・子連れでイベントに参加したい方等
・お子様とワークショップに参加したい方等
・工芸品の新しい展開に興味のある方等
・子ども向けのモノづくりに関心のある方等
・その他、本イベントに関心のある方等
▼主催:復興庁 企画運営:NECソリューションイノベータ株式会社(受託事業者)
※「Fw:東北」は「進む」の意味を「フォワード」に置き換えた東北における共創によるプロジェクト全体の愛称です。被災地復興及び地域課題の解決に取り組んでいるNPO、企業、自治体等が、自らの取組を加速・発展させるため、共創の手法を通じて、新たなパートナーとのつながりを創出し、地域社会の課題解決を目指していきます。
※「Fw:東北Weekly」では、復興庁、「新しい東北」官民連携推進協議会による、「Fw:東北」の取組み、プロジェクトをご紹介し、東北で様々なテーマを掲げて行われている活動や、それらに取り組む人々にフォーカスを当て、認知向上や共創の輪を広げる活動として、各種イベントを、東京や東北各地で多数展開(年間30本程度を予定)します。
※内容は予告なく変更になる可能性があります
7月30日(月)大船渡市市民防災観光交流センターにて、「3.11メモリアルネットワーク~被災3県で学びあう震災伝承~」を開催しました。
東日本大震災発災から7年の経過とともに、岩手・宮城・福島各県において震災遺構や祈念公園の整備がすすめられ、各地で活動している語り部さんなど、伝承担い手同士の連携の機運が広がってきています。今回は、3.11メモリアルネットワークさんと弊法人いわて連携復興センターが共催し、復興庁 被災者支援コーディネート事業を活用して開催致しました。
3.11メモリアルネットワークとは、東日本大震災の伝承に携わる個人・団体からなる民間の広域ネットワーク組織で、将来にわたる継続的な伝承活動を支え、社会の困難に立ち向かう活力ある人・地域づくりに取り組むことを目的に、昨年の11月に発足したものです。岩手県での第一回目となるこの日は、40名以上の方々にご参加いただきました。
始めに、参加者の方々の参加目的やそれぞれの地域・団体の課題などを、団体紹介でお聞かせいただきました。その後、宮城県石巻市を中心に活動している3.11メモリアルネットワークさんの活動紹介や設立の趣旨などの説明がありました。
その後、参加者の皆さんから積極的、かつ建設的な意見交換がなされ、終了後の名刺交換交流会でも、たくさんの交流や今後の連携についても意見が交わされていました。
震災から7年にわたり取り組んできたそれぞれの団体の軌跡やノウハウを、被災3県が手を携えて繋がっていくことを願いながら、閉会となりました。
私たちいわて連携復興センターは、岩手で復興支援を行う主にNPOの皆さんに、ノウハウや情報やネットワークなど色々な活動資源をコーディネートさせて頂いております。今回は、岩手で伝承をテーマに活動している皆様に、宮城をスタートとして3県の広域の伝承ネットワークを築こうとしている「3.11メモリアルネットワーク」さんの構想を聞いて頂き、活動の促進や同じテーマで活動する団体同士がつながる場として開催させていただきました。
今後も、地域を超えた支援者間の情報共有の場を創出してきたいと思います。
| 名称 |
平成 30 年度NPO等による復興支援事業費補助金(一般枠・二次募集)
|
|---|---|
| 内容 |
1 趣旨
多様な担い手が協働・連携して行う地域課題解決の取組を推進するため本事業を実施するもの。
2 補助対象事業
平成30年10月以降に開始する次の(1)~(3)までのいずれかに該当する事業であること。
(1)地方自治体との協働
従来は地方自治体が担ってきた公の分野における活動をNPO等が
地方自治体と協働して行う事業
(2)中間支援団体による支援
中間支援NPOが他の団体を支援するための事業
(3)企業との連携
企業のCSR活動と連携する事業
|
| 補助金額 |
・事業費の8/10 以内、補助金の上限額は 800 千円(消費税額等を含む。)
・若干数(4事業程度)
|
| 募集期間 |
平成30年8月2日(木曜日)~ 平成30年8月27日(月曜日) 午後5時必着
|
| お問合せ先 |
岩手県環境生活部若者女性協働推進室 NPO・協働担当
|
| URL | http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/067015.html |
| 名称 |
平成 30 年度NPO等による復興支援事業費補助金(復興枠・二次募集)
|
|---|---|
| 内容 |
1 趣旨
復興支援及び被災者支援を行うNPO等による絆力を活かした取組を支援することにより、行政では手の届きにくいきめ細やかな復興・被災者支援を図るため、復興・被災者支援活動等を行うNPO等への事業費助成を行います。
※平成 30 年 10 月以降に開始する事業が対象です。
2 補助対象事業
平成30年10月以降に開始する次の(1)から(3)までのいずれかに該当する事業
(1)岩手県における復興・被災者支援又は岩手県から他の都道府県への避難者に対する支援
(2)原子力災害に係る岩手県に対する風評被害対策の取組を行う事業
(3)(1)又は(2)のいずれかに取り組むNPO等への支援
|
| 補助金額 |
事業費の 9/10 以内とし、上限額は 6,750 千円
若干数(6事業程度)
|
| 募集期間 |
平成30年8月2日(木曜日)~8月27日(月曜日)午後5時必着
|
| お問合せ先 |
岩手県環境生活部若者女性協働推進室 NPO・協働担当
|
| URL | http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/067017.html |
| 名称 |
<平成30年7月豪雨被災地支援>NPO・ボランティア活動支援
|
|---|---|
| 内容 |
・専門的な支援を行うNPO等の活動(医療・福祉、水害復旧作業に係る技能を有する分野)
・特別なニーズ(障害者・高齢者・乳幼児・外国人などの要配慮者)に対する専門性を活かした活動
・被災地と連携しボランティア不足を解消するための仕組み等を構築・実施する活動
|
| 助成金額 |
1事業あたり50万~300万円
|
| 募集期間 |
2018年8月31日(金)まで(決定は随時行います)
|
| お問合せ先 |
日本財団事務センター 平成30年7月豪雨災害担当
|
| URL | https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/nishinihon/support/ |
西日本豪雨災害への対応について、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の依頼により、
いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)の一員として、
いわて連携復興センターより大向昌彦が愛媛県(主に宇和島市・大洲市・西予市)に入りました。
主にJVOADとともに、県、各市行政・社協との調整、活動団体の把握、情報共有会議運営に従事する予定です。
派遣期間は7月28日~8月10日です。
なお、いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)からは、
細川加奈子(遠野まごころネット)が岡山県へ、井上恵太(遠野まごころネット)が広島県へそれぞれ支援に入っています。
また、8月6日から11日まで、共同代表 寺井良夫が愛媛県大洲市にて災害ボラセン運営のサポートを行う予定です。
INDSの活動は下記をご覧ください。
https://www.facebook.com/IDRNPONW/
日を追うごとにメディアでの報道が少なくなっていますが、
西日本豪雨の被災地では、まだまだ支援が必要な状況と聞きます。
皆様におかれましても、できる範囲の支援を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
| 名称 |
平成30年度(第25回)ボランティア活動助成募集
|
|---|---|
| 内容 |
・高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動
※平成27年度以降(第22回~24回)の受贈団体は、応募資格がありません。
・地震・豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支援活動
※過去の助成を受けた時期での応募制限はありません。
※大規模自然災害とは、「東日本大震災」「平成28年熊本地震」「平成29年7月九州北部豪雨」「大阪府北部地震」「平成30年7月豪雨」等
<応募資格>
ボランティア活動を行っているメンバーが5名以上で、かつ営利を目的としない団体
(任意団体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等)。
|
| 助成金額 |
上限30万円(1団体あたり)
総額4,500万円
|
| 募集期間 |
平成30年8月1日(水)~9月15日(土)当日消印有効
|
| お問合せ先 |
公益財団法人大和証券福祉財団 事務局
|
| URL | http://www.daiwa-grp.jp/dsf/ |
| 名称 |
平成30年度(第1回)子ども支援活動助成
|
|---|---|
| 内容 |
子ども(18歳未満)への支援活動
<助成対象の活動例>
子ども食堂の運営
子どもがいる貧困家庭への食糧支援(フードバンク)
子どもの体験支援および学習支援活動
子どもへの虐待防止活動
子どもの非行、いじめ、不登校、引きこもりに対する支援活動
子どもへの読み聞かせ、人形劇等の活動
子どもの居場所づくりの運営
発達障がい等の障がい、難病を抱える子どもへの支援活動
子どもの電話相談活動
子どもの見守り活動
※主な支援活動が「子ども」対象であれば、高齢者等が参加される活動も助成の対象となります。
|
| 助成金額 |
金額:上限50万円(1団体あたり) 総額500万円
期間:1団体あたり最大3年間 最大助成額(1団体あたり)150万円
※継続支援に際し、毎年、審査を実施いたします。
|
| 募集期間 |
平成30年8月1日(水)~9月15日(土)当日消印有効
|
| お問合せ先 |
公益財団法人大和証券福祉財団 事務局
|
| URL | http://www.daiwa-grp.jp/dsf/ |
| 名称 | 第6回「エクセレントNPO」大賞 |
|---|---|
| 内容 |
本賞は、NPO活動の質の向上をめざして努力している団体を、評価を通じて社会に“見える化”し、良質な支援が集まる好循環を生み出すことが目的です。
また、応募されたすべての団体の自己評価書(応募用紙)に対してフィードバック・レター(自己評価に対するコメント)をお送りしています。
【応募資格】
国内外における社会貢献を目的とした市民による日本国内のNPOなど種々の民間非営利組織(法人格の有無不問) ※自薦・他薦可
|
| 特典 |
◆ エクセレントNPO大賞
部門賞受賞者から選出されます。
賞状、賞金30万円(部門賞賞金50万円にプラス)、毎日新聞特集記事で紹介
◆部門賞
市 民 賞: 賞状、賞金50万円
課題解決力賞: 賞状、賞金50万円
組 織 力 賞: 賞状、賞金50万円
◆表彰式には、すべてのノミネート団体(15団体ほど)が招待され、各団体を紹介のうえ、賞状が授与されます。
|
| 応募期間 | 2018年7月31日(火)~ 9月14日(金)必着 |
| お問合せ | 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議事務局 |
| URL | http://www.excellent-npo.net/ |
認定NPO法人イーパーツ様より第17回複合機およびラベルライター寄贈プログラムのご案内です。
以下、転載
=============================================
【NPO法人イーパーツ】 寄贈プログラム公募のご案内
第17回複合機およびラベルライター寄贈プログラム(8/21まで)
=============================================
NPO法人イーパーツでは、情報化支援を目的としたパソコンおよび周辺機器の
寄贈プログラムを行なっています。
本日は「第17回複合機ラベルライター寄贈プログラム」のご案内です。
この機会にぜひ申請をご検討ください、お待ちしております。
--------------------------------------------------------------
第17回複合機およびラベルライター寄贈プログラム(8/21まで)
--------------------------------------------------------------
【公募期間】2018/7/21~2018/8/21(当日消印有効)
【寄贈内容】
電話機付インクジェットFAX複合機、A3両面対応インクジェット複合機、
インクジェット複合機、モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、
ラベルライターなど計52台です。すべてブラザー製です。
【費 用】1台あたり1,000円~5,000円(機種によって異なります)
【詳細、申込み方法】下記URLをご参照ください。
http://www.eparts-jp.org/program/2018/07/device-17th.html
-----
【問合せ先】
認定NPO法人イーパーツ
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-55-8 パレグレイス501
TEL:03-5481-7369(PM1~5) / FAX:03-6805-2728
URL: http://www.eparts-jp.org / E-mail: info@eparts-jp.org
次のとおり標記に係る受託希望者を募集します。
■業務目的
地域の見守り資源等の実態を把握し、県内の各地域の分析を行うことにより、今後の本県の東日本大震災津波被災者に対する見守りや地域の支え合い等の支援のあり方について、県の方向性を検討するうえでの基礎資料とするため、見守り活動を行っている団体の取組状況等について調整を行うものです。
■業務名
平成30年度被災者地域見守り資源等の実態調査業務
■委託期間
契約締結の日から平成31年1月31日まで
■委託料の上限額
2,298千円(税込み)
■スケジュール
質問票の提出期限 8月6日(月曜日)
質問に対する回答期日 8月9日(木曜日)
企画提案提出期限 8月20日(月曜日)
企画提案審査 8月下旬
企画提案結果通知 8月下旬
契約手続き 9月上旬
詳細・お申し込みは以下リンク先をご覧ください。
http://www.pref.iwate.jp/nyuusatsu/compe/sanka/066744.html
岩手県は近年、東日本大震災・台風10号豪雨災害などの自然災害を経験し、発災後の支援活動におけるニーズや課題を通じ、平時から災害に対する備えの重要性を痛感しました。また、災害ボランティアセンター設置後のボランティア活動において、床下浸水した家屋の泥出し手順等について支援者側が把握できていない現状でもあります。
本研修は、行政・社協・NPOや市民が合同で床下浸水した家屋の泥出し等に関する基礎知識を学び、ワークでの実技を通じ効果的な手順を取得します。また、研修の学びから地域の防災力を向上させるとともに、今後起こりうる災害時に迅速なボランティア活動の実現と、一日も早い被災者の生活再建につなげることを目的とします。
大阪府北部地震、西日本豪雨災害など今年に入り大規模な災害が頻発している状況の中、次に起こりうる災害への備えにつながる貴重な機会と捉えております。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。
床下浸水した家屋の泥出し等に関する基礎知識取得研修
日時:平成30年8月25日(土) 10:30~15:00(開場10:00~)
場所:社会福祉法人 雫石町社会福祉協議会
対象:⑴県・市町村行政防災(災害)担当課
⑵市町村社会福祉協議会職員
⑶NPO団体職員、個人ボランティア等テーマに関心のある方
参加費:無料
参加者定員:30名程度
参加申込期限:8月22日(水)18:00まで
主催:特定非営利活動法人いわて連携復興センター
協力:
社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会
社団福祉法人 雫石町社会福祉協議会
いわてNPO災害支援ネットワーク
後援:岩手県
事務局:
特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向
〒024‐0061 岩手県北上市大通り1‐3‐1 おでんせプラザぐろーぶ4F
Tel:0197‐72‐6200 Fax:0197‐72‐6201
E-mail:ohmukai@ifc.jp
申込用紙にご記入いただき、0197-72-6201にFAXいただくか
氏名・所属・ご連絡先をご明記の上、ohmukai@ifc.jpまでご連絡ください。
※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「8/25 研修参加申込」としてお送り願います。
本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」を特定非営利活動法人いわて連携復興センターが受託し、開催するものです。
プログラム
10:30~12:00
講義:「技術系ボランティアに係る知識と安全衛生」
・近年の災害における技術系支援の連携事例
近年の大規模災害(熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨など)から、災害ボランティア活動の特徴や技術系NPOと災害ボランティアセンターの連携についてお話しいただきます。
・ボランティア活動と安全衛生
ボランティア活動やボランティアコーディネートを行う上での安全衛生・危険予知に関するワークショップを行います。
講師:
風組関東 代表 小林 直樹 氏
一般社団法人OPEN JAPAN 副代表 肥田 浩 氏
12:00~13:00
昼食・休憩
13:00~15:00
講義&実技(ワーク):「床下対応基礎講習」
災害ボランティア活動で使用する資機材の取り扱い、災害ボランティア向けの装備と資機材に関する知識を踏まえ、床下泥出しに関する一連の流れを体験します。
講師:
風組関東 代表 小林 直樹 氏
一般社団法人OPEN JAPAN 副代表 肥田 浩 氏
トヨタ財団では、平成30年9月1日~10月10日にかけて「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ― 地域に開かれた仕事づくりを通じて―」をテーマに 「国内助成プログラム」の公募を実施します。国内助成プログラムは、 地域課題解決とその担い手育成を目的に、事業実施に向けた調査を対象とした「しらべる助成」と事業を対象とした「そだてる助成」の二つの枠組みを設定しています。
地域の課題は、単体で発生することはなく複数の要因が絡み合って生じていることが多いと思います。それゆえ、地域課題の解決を実現するためには、まずはじめにその課題の問題構造(背景や要因)や関係者を把握するなどが重要と考えます。トヨタ財団「国内助成プログラム」で「しらべる助成」という枠組みを設定しているのはそうした問題意識によるものです。
公募説明会では、トヨタ財団担当者より、国内助成プログラムの趣旨や具体的な助成事例をご説明するとともに、特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センターの若菜千穂常務理事より、NPO等が行う調査や事業の組み立て等についてお話をいただきます。個別相談にも対応いたしますので、ご応募をご検討の方はお気軽にぜひご参加ください。
トヨタ財団国内助成プログラムの募集要項・企画書は、トヨタ財団のウェブサイト
https://www.toyotafound.or.jp/ に掲載されています。
*特に個別相談をご希望される方は、ご一読の上ご参加頂けましたら幸いです。
【日 時】
平成30年8月20日(月)13:30~16:00(開場13:00)
【会 場】
いわて県民情報交流センター(アイーナ) 研修室810
(〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号)
【内 容】
・トヨタ財団国内助成プログラムのご紹介
・ミニ講義「事業の組み立てから、スタート・モニタリングまで」
特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター 常務理事 若菜千穂 氏
・全体質疑&相談
・個別相談
【申込期限】
平成30年8月17日(金)18:00
【参加費】
無料
【定員】
30名(事前予約制)※参加者定員になり次第予約を締め切らせていただく場合がございます
【お問合せ/お申込み】
〒024‐0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4F
Tel.0197-72-6200 Fax.0197-72-6201
申込用紙をご記入いただき、0197-72-6201にFAXいただくか
必要事項をご明記の上、 n.segawa@ifc.jp までご連絡ください。
※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「公募説明会盛岡申込」としていただき、
お名前、会社名(所属先)、連絡先をご記入ください。
岩手日報社様より、復興に関する取り組みをしている団体を顕彰する「東北みらい賞」のご案内です。
今年度から公募(自薦・他薦どちらもOK)となったそうです。
是非ご活用ください。
東北みらい創りサマースクール2018 『東北みらい賞』公募要領
東北みらい創りサマースクールは「震災の記憶を風化させず、教訓を未来につなげていく」ことを目的に2012年に始まりました。東日本大震災の教訓を後世に伝え被災した地域の復興支援と地域創生に携わる人材育成を目指し、地元大学・メディア・民間企業等の有志が「東北みらい創り実行委員会」を組織し、毎年開催しています。
本実行委員会では「東北みらい賞」を創設し、被災地に根差して復興活動をされ、顕著な実績を上げている個人・団体の中から、これまで15人(団体)を顕彰してまいりました。
本賞は東日本大震災のような大規模災害からの復興活動は、長期間にわたり地域に根差して継続的に行われなければならず、活動を実践する人(団体)を支えていくことが人材育成の観点からも重要であるという観点から顕彰するものです。
【応募資格】岩手県内で復興に関わる活動をしている個人・団体
【賞の構成】東北みらい賞 3人(団体) 賞状と賞金(5万円)
【応募方法】推薦・自薦書に必要事項をご記入の上、メールにてご応募ください。
【応募先】 東北みらい創りサマースクール実行委員会 junimai@iwate-u.ac.jp
【選考方法】東北みらい賞審査員で構成する審査会により選考します。
【発表方法・期日】2018年9月14日(金)まで受賞者にのみ連絡します。
【表彰式日程】2018年9月30日(日)(予定)
【表彰式会場】遠野みらい創りカレッジ(遠野市土淵・旧遠野市立土淵中学校)
【応募締切】2018年8月10日(金)必着
【お問合せ】
東北みらい創りサマースクール実行委員会
事務局:〒020-8551 盛岡市上田4丁目3-5 岩手大学三陸復興・地域創成推進機構内
電話:019(621)6491 / FAX:019(621)6493
7月20日(金)、陸前高田市にて「第2回現地会議in東北-全国を巻き込む、担い手をはぐくむ―」を開催致しました。
いわて連携復興センターは、JCN岩手担当として参画しており、今回の現地会議はJCNと共催での開催となりました。
当日は、当日は岩手・宮城・福島で活動する方々を中心に25団体39名のご参加をいただきました。
これまで現地会議は、被災地・被災者を支援している団体間の連携を促し、
支援活動を続けるうえで抱える問題や課題を共に考える場として、岩手県・宮城県・福島県にて定期的に開催しています。
今回の第2回現地会議in東北では、地域にある「課題」と「解決策」、そしてそれを担うべき「人物像」について広域で考え、地域内外からの「多様な関わり方」について整理及び可視化し、広く発信・提案していくための機会としました。
当日は、
第1部:基調講演「『関わり方を提案していく』ということ」
岡本翔馬 氏(認定NPO法人桜ライン311 代表理事)
第2部:事例報告「私が伝えたい『担い手と関わり方』」
【岩手県】
鈴木悠太 氏(NPO法人クチェカ 事務局長)
戸塚絵梨子 氏(株式会社パソナ東北創生 代表取締役)
【宮城県】
石井優太 氏(公益財団法人共生地域創造財団 事務局長)
小野寺真希 氏(合同会社moyai コミュニティデザイナー / 気仙沼まち大学運営協議会 地域おこし協力隊)
【福島県】
青木淑子 氏(NPO法人富岡町3・11を語る会 代表)
中鉢博之 氏(NPO法人ビーンズふくしま 常務理事・事務局長)
第3部:グループワーク「全国を巻き込む、担い手をはぐくむ」
の3部構成に加え、西日本豪雨災害について、現状とこれからを「知る」時間を設けました。
基調講演では、桜ラインの考える担い手とはどういう人たちか、多様な資源を巻き込むためにしている関わり方の提案について、そして実際に巻き込む方法について、お話しして頂きました。
事例報告では、各地域で活動している中で感じている「課題」と解決するために必要な担い手、地域外へ提案したい「関わり方」についてお話を頂きました。
「担い手」についての捉え方も様々で、活動分野によって全国に求める関わり方も異なることが特徴的であったと感じています。
西日本豪雨災害については、
・全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)
・いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)
からの現状報告とこれからについてお話しがありました。
府県をまたぐ広域な被害であり、地域間での支援のムラが出てくることも課題として出されました。
東日本大震災や台風10号被害等での経験を西日本でも活かせるように、
岩手、宮城、福島から出来る西日本への支援のカタチを考えていきたいと思っています。
グループワークにおいても様々な意見が出されました。
より多くの人に伝えていくためにも、改めて、地域団体への訪問(ヒアリング)を重ね、現地会議in東京などにつなげていきたいと思っております。
復興庁様主催のアイディアソンのご案内です。
[Fw:東北Weekly vol.10]工芸品の未来を考えるアイデアソン
~東北の工芸品の担い手育成の課題とは~
関連地域: 福島県浪江町・宮城県仙台市
【地域課題】
東北には各地に特徴のある工芸品が多数存在します。時をまたぎ、人々の暮らしの中で長らく親しまれてきた工芸品も、発災以降の市場や環境の変化により、担い手育成への新たなアプローチが求められています。
【企画趣旨】
個性豊かな地域の工芸品を守り、育てていく担い手は、そのように生まれ、増やしていくことができるのか。今回のFw:東北Weeklyでは、異業種からの転身によって工芸品の世界へ身を投じ、新たな価値づくりを仕掛ける大堀相馬焼松永窯の四代目を継ぐ松永さんと、仙台で近代に生まれた伝統的工芸品、玉虫塗を担う東北工芸製作所の佐浦さんゲストに迎え、地域の工芸品の担い手を増やすためのアイデアをみなさんと一緒に考えていきます。
▼日時:2018年7月26日(木)19:00-21:00(開場 18:30)
▼会場:スマートニュース株式会社
(東京都渋谷区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル 2F)
※アクセス 渋谷駅徒歩12分、原宿駅徒歩9分、明治神宮前駅徒歩7分
▼定員:30名
▼参加費:無料
▼参加申込:下記URLよりお申し込みください。
【URL】http://goo.gl/Yu1Fjx
▼登壇者 ※順不同/敬称略
松永武士(大堀相馬焼窯元「松永窯」4代目/株式会社ガッチ 代表取締役)
1988年生まれ。福島県浪江町出身。明治43年創業の大堀相馬焼の窯元「松永窯」4代目。慶應義塾大学在学中に起業し、中国、香港、カンボジア等、海外を舞台にヘルスケア関連事業を展開。震災で打撃を受けた大堀相馬焼の再生を手掛けるべく、海外事業を譲渡し帰国。ビジネスのフィールドを大堀相馬焼の復活に賭け、大堀相馬焼の企画販売から技術の伝承まで、活動の幅を拡げている。復興庁平成28年度「新しい東北」復興功績顕彰「企業による復興事業事例」に選定された。
佐浦みどり(有限会社東北工芸製作所 常務取締役・店長)
岩手県盛岡市生まれ。東北学院大学法学部を卒業。東北工芸製作所へ入社ののち、2005年より店長、2013年より常務取締役兼店長に就任。昭和の戦前期に商工省工芸指導所と東北帝国大学金属材料研究所の協力によって生まれ、仙台を代表する工芸品として玉虫塗の生産を行う東北工芸製作所で、佐浦家の家業を継承する社長を支えながら、店舗の運営と販売に関する責任者として重責を担う。
▼プログラム(予定)
19:00 開会メッセージ
19:05 キーノート「大堀相馬焼の存続を目指して」(仮)
スピーカー: 松永武士氏
19:25 ミニアイデアソン「若者が工芸品の担い手に挑戦する仕組みを考える」
インプットトーク「東北工芸製作所、玉虫塗の挑戦」(仮)
スピーカー:佐浦みどり氏
20:40 LIKEorJOIN/コミットメントカード記入
20:50 Fw:東北活動紹介/閉会メッセージ
▼参加対象者:
・震災をきっかけにしたつながりから新しいビジネス創出に関心がある方等
・工芸品の新しい展開に興味のある方等
・地域産業の担い手づくりに関心のある方等
・その他、本イベントに関心のある方等
▼主催:復興庁 企画運営:NECソリューションイノベータ株式会社(受託事業者)
※「Fw:東北」は「進む」の意味を「フォワード」に置き換えた東北における共創によるプロジェクト全体の愛称です。被災地復興及び地域課題の解決に取り組んでいるNPO、企業、自治体等が、自らの取組を加速・発展させるため、共創の手法を通じて、新たなパートナーとのつながりを創出し、地域社会の課題解決を目指していきます。
※「Fw:東北Weekly」では、復興庁、「新しい東北」官民連携推進協議会による、「Fw:東北」の取組み、プロジェクトをご紹介し、東北で様々なテーマを掲げて行われている活動や、それらに取り組む人々にフォーカスを当て、認知向上や共創の輪を広げる活動として、各種イベントを、東京や東北各地で多数展開(年間30本程度を予定)します。
詳細・お申込みは以下Facebookページよりご覧ください。
https://www.facebook.com/fwtohoku/
第10回 岩手発 手しごと絆フェア
東日本大震災津波からの復興支援を目的に、被災地で暮らす人たちによる手しごと品の販売会「第10回 岩手発 手しごと絆フェア」が7月19日(木)~23日(月)、盛岡市菜園のパルクアベニュー・カワトクにて開催されます。
開催期間中は、手しごと絆フェア会場内で2,000円(税込)以上お買い上げの方が1回福引できる、恒例の福引大会を行います。※ハズレあり
[第10回 岩手発 手しごと絆フェア]
■開催期間:平成30年7月19日(木)〜23日(月)
■時 間:10:00~19:00 ※最終日は17:00まで。
■場 所:パルクアベニュー・カワトク1F/エレベーターホール
(岩手県盛岡市菜園1-10-1)
http://www.kawatoku.com/saiji/main/index.html
○主催:colle-color
○後援:盛岡市
○協力:株式会社川徳、いわて生協、MCL専門学校グループ
| 名称 | 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト2018 |
|---|---|
| 内容 |
復興庁が平成 25 年 12 月に設立した「新しい東北」官民連携推進協議会では、被災地の産業復興に向けた地域産業の創出の機運醸成を図ることを目的に、平成 26 年度より「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催しております。
今年度も『「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2018』の開催を決定し、この度、被災地における地域産業の復興や地域振興に資する事業(すでに取り組んでいるもの、これから取り組もうとしている事業計画の両方を含みます。)の募集を開始しました。
(1)一般の部
① 応募いただける方
(2)「学生の部」の対象となる方以外どなたでもご応募いただけます。
② 募集分野
東日本大震災の被災地における地域産業の復興、地域振興に資する実施段階の
「事業」または計画段階の「事業計画」を募集します。募集分野は以下の通りです。
1)水産業(加工業を含む)
2)農林畜産業(加工業を含む)
3)製造業(食品加工業を除く)
4)商業・サービス業等
5)観光業
6)その他(エネルギー、ソーシャルビジネス、住まい・暮らし等)
以下のような事業・事業計画が対象です。
1)新たに震災後から取り組んでいる事業または事業計画
2)被災を乗り越え、被災前からの従前の土地や移転先の新たな土地での再起を図る事業または事業計画
3)東北地方の地域経済や産業の成長につながる事業または事業計画
4)その他、「新しい東北」の実現に向けた様々な事業または事業計画
(2)学生の部
① 応募いただける方
学生(※)の方であればどなたでもご応募いただけます。
(※)「学生」とは、学生(大学・大学院、高等専門学校、専修学校、各種学校及び高等学校
(中等教育学校後期課程を含む)の学生・生徒)であり、応募者が上記の学生によるグループ、団体とします。
② 募集要件
学生が主体となって企画した事業計画を募集します。
「一般の部」のように募集分野は設けておりませんが、「学生の部」の募集要件は
以下の通りです。
1)応募者が学生(大学・大学院、高等専門学校、専修学校、各種学校及び高等学校
(中等教育学校後期課程を含む)の学生・生徒)又は学生によるグループ、団体であること
2)まだ事業化されていない事業計画であること
3)事業計画が、被災地の地域資源を活用するもの、被災地の地域課題の解決に資するもの、被災地内外の交流を創造するものなど、被災地での実施を想定したものであること
|
| 助成金額 |
(1)副賞
(2)PR の実施
(3)PR 機会の提供
(4)その他の特典のご提供
(1)~(3)の特典に加え、受賞された方に下記の特典のご提供を検討しています。
<支援メニュー>
①専門家による派遣指導(3 団体まで)
②プロモーション活動支援セミナーへのご案内(全 3 回を予定)
③クラウドファンディング実施支援
④各種展示会出展経費支援
⑤チャレンジショップ出店経費支援
※受賞した賞の内容によって、ご利用いただける特典に制限があります。
|
| 募集期間 | 平成30年8月3日(金)17時必着 |
| お問合せ先 | 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト事務局 |
| URL | https://www.newtohoku.org/bcontest/BC_summary2018.html |
岩手県保健福祉部地域福祉課様より企画提案募集のご案内です
「コミュニティ食堂支援事業」に係る企画提案募集について
業務概要
(1) 事業名
コミュニティ食堂支援事業
(2) 委託期間
委託契約日から平成31年3月31日まで
(3) 委託料上限額
4,174千円(税込)
スケジュール
(1) 企画提案募集開始 平成30年7月11日(水)
(2) 質問票の提出期限 平成30年7月17日(火)
(3) 質問票に対する回答期限 平成30年7月20日(金)
(4) 企画提案書等提出期限 平成30年7月27日(金)
(5) 企画コンペの実施 平成30年8月2日(木)
(6) 委託契約締結 8月上旬
詳細・お申し込みは以下リンク先をご覧ください。
http://www.pref.iwate.jp/nyuusatsu/compe/sanka/066442.html