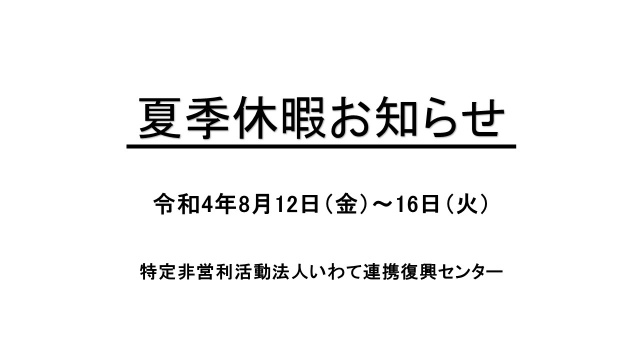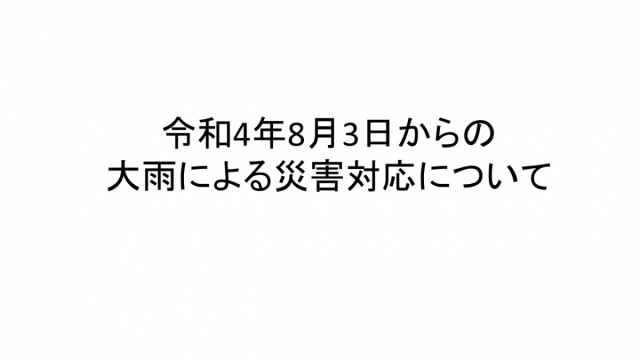| 名称 |
令和5年度 花博自然環境助成
|
|---|---|
| 内容 |
1990年(平成2年)に大阪・鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会の「自然と人間との共生」という理念の継承発展・普及啓発につながる調査研究や活動・行催事を支援し、潤いのある豊かな社会の創造に寄与することを目的として、以下により令和5年度に実施する助成事業の公募を行います。
復興活動支援分野は活動行催事分野に統合しました。
国際花と緑の博覧会の「自然と人間との共生」という理念の継承発展または普及啓発に資する事業であって、生命の象徴としての「花と緑」に関連する広汎な分野おいて、科学技術または文化の発展、交流及び災害復興に寄与するもを対象としています。
●応募対象者:
(1)公益・一般財団法人、公益・一般社団法人
(2)特定非営利活動法人(NPO)
(3)人格なき社団のうち非収益団体であって代表者の定めがあるもの。
(研究グループ、実行委員会、活動クラブ、友の会、ボランティア団体など。)
※ 日本国内に活動の場を有する団体であること。
※ 応募しようとする事業の実施者であること。
※ 営利を目的とせず、公益性を有する事業を実施する団体であること。
※ 応募する事業にかかわる何らかの活動実績を有している団体であること。
※ 国や地方公共団体、独立行政法人、民間企業、学校法人でないこと。
※ 特定の政治、思想、宗教等の活動を主たる目的とした団体でないこと。
※ 暴力団でないこと、暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
※ 同じ事業について、令和2年度~令和4年度の3ヵ年度に連続して助成を受けていないこと。
※ 一団体につき一件の応募とします。
※ 国や地方公共団体の指定管理業務についての応募は受け付けることができません。
|
| 助成金額 |
調査研究 一件当たり100万円以内で、4分の3以内
活動・行催事 一件当たり50万円以内で、4分の3以内
|
| 申込期限 |
2022年9月9日(金)※当日消印有効
|
| お問合せ |
公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 企画事業部企画事業課
|
| URL | https://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_05.html |
| 名称 |
2022年度 第二期 団体活動支援助成
|
|---|---|
| 内容 |
この助成は、団体(民間企業を含む)及びグループによって行われる食物アレルギーの問題解決を目指す活動を支援することで、食物アレルギーに関係する環境改善を進めることを目的とします。
●対象活動領域:
本助成の目的を達成するため、以下の対象領域を設定する。
①食物アレルギー対応食品の開発や普及のための調査研究 ②食物アレルギーに関する啓発イベントの開催 ③食物アレルギーに関する啓発物(冊子、その他)の制作及び普及 ④食物アレルギーに関する災害時対策 ⑤食物アレルギーに関する研究会・講演会・シンポジウム等の開催 ⑥その他、食物アレルギーに関する啓発に役立つ活動 ※具体的な活動を対象とします。団体そのものに対する賛助金、協賛金、年会費等は対象となりません。 ※非営利的な目的で行われる公益性の高い活動を対象としています。 ※書籍等の出版(印刷)を目的とする申請課題は、制作物の内容を判断するための情報(例.プロトタイプや原稿)の提出を必須とします。
●応募資格:
国内の法人及び団体を対象とします。法人格や公的機関か民間かは問いませんが、科学に基づいた正確な知識を元にした応募を促すため、推薦人(医師、管理栄養士、小児アレルギーエデュケーター、食物アレルギー管理栄養士等)を必須とします。
※反社会的勢力とは一切関わっていないこと、また、活動内容が政治、宗教、思想に偏っていないことを要件とします。
●助成期間:2022年11月1日(火)から2023年6月30日(金)に行われる活動
|
| 助成金額 |
助成件数:最大約10件
1件あたりの上限は定めませんが、期待される効果に対する支出費用、資金計画の妥当性、自助努力(自己資金)の有無も審査対象となります。
また、助成の対象となった場合にも、実際の助成金額は申請金額より減額されることがあります。
|
| 申込期限 |
2022年9月2日(金)※当日消印有効
|
| お問合せ |
公益財団法人ニッポンハム食の未来財団 団体活動支援助成事務局(担当:小泉・織田島)
|
| URL | https://www.miraizaidan.or.jp/general_public/grants/2022/01.html |
| 名称 |
子供の未来応援基金 令和5年度 未来応援ネットワーク事業 B
|
|---|---|
| 内容 |
平成27年度より、「子供の未来応援国民運動」の一環として、民間資金からなる「子供 の未来応援基金」を通じて、貧困の状況にある子供たちの実態を把握しやすい、草の根で活動を行うNPO法人等の運営基盤の強化・掘り起こしを行い、社会全体で子供の貧困対策を進める環境を整備することを目的に、NPO法人等への支援金交付を行っています。 本基金による支援を行う中、単年度の事業費が少額の団体に対する支援の強化を求める声が寄せられていたことに鑑み、令和2年度(第 4回未来応援ネットワーク事業)から、小規模での活動を行う団体に対して、より一層の支援をすべく、小規模支援枠を設け、支援を実施しております。 本事業Bは、こうした趣旨を踏まえ、草の根で活動する団体の運営基盤の強化等に資するための支援金の交付を行うものです。
●対象となる団体:
社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人又は団体であって、過去に未来応援ネットワーク事業の支援を受けたことがなく(令和2年度(第4回未来応援ネットワーク事業)以降の事業Bによる支援を除く)、設立後 (前身団体がある場合は前身団体設立後)5年以内の法人等、または新規事業もしくは実施後間もない事業(事業開始から2年以内)を実施する法人等
ア 公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
イ NPO法人(特定非営利活動法人)
ウ 一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)
エ その他ボランティア団体や町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う任意団体
●対象となる事業:
応募する法人等が自ら主催する事業であり、次のアからカまでに該当する子供の貧困対策のための事業(金銭を直接給付する事業又は貸与する事業を除く。)を支援金の交付対象事業として募集いたします。
ア 様々な学びを支援する事業
イ 居場所の提供・相談支援を行う事業
ウ 衣食住など生活の支援を行う事業
エ 児童又はその保護者の就労を支援する事業
オ 児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業
カ その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
(上記アからカまでに示す事業は、子供の貧困対策に係る事業である必要があるが、同時に、児童虐待や青少年育成における課題など、子供の貧困の背景に存在する様々な社会的要因の解消にも資する内容を伴う事業についても申請が可能。)
●支援対象期間:2023年4月1日から2024年3月31日までとします。
|
| 支援金額 |
30万円又は100万円
|
| 申込期限 |
2022年9月20日(火)※15:00(応募フォーム登録完了)
|
| お問合せ |
独立行政法人福祉医療機構 NPOリソースセンター NPO支援課
|
| URL | https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5/ |
| 名称 |
子供の未来応援基金 令和5年度 未来応援ネットワーク事業 A
|
|---|---|
| 内容 |
貧困の状況にある子供たちの抱える困難やニーズは様々であり、貧困の連鎖を解消するためには、制度等の枠を越えて、一人ひとりの困難に寄り添ったきめ細かな支援を弾力的に行うことが必要です。また、コロナ禍が子供たちの環境にも大きく影響していることにも留意する必要があります。 これらを踏まえると、貧困の状況にある子供たちの実態を把握しやすい、草の根で支援活動を行うNPO法人等の存在が重要ですが、そうしたNPO法人等の多くは、財政的に厳しい運営状態にあり、行政や民間企業等との連携や支援を求められているものと認識しています。 この事業は、「子供の未来応援国民運動」の一環として平成27年度に創設されており、 民間資金からなる「子供の未来応援基金」を通じて、草の根で支援活動を行うNPO法人等の運営基盤の強化・掘り起こしを行い、社会全体で子供の貧困対策を進める環境を整備することを目的に、NPO法人等への支援金の交付を行うものです。
●対象となる団体:
社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人又は団体
ア 公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
イ NPO法人(特定非営利活動法人)
ウ 一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)
エ その他ボランティア団体や町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う任意団体
●対象となる事業:
応募する法人等が自ら主催する事業であり、次のアからカまでに該当する子供の貧困対策のための事業(金銭を直接給付する事業又は貸与する事業を除く。)を支援金の交付対象事業(以下「支援事業」という。)として募集いたします。
ア 様々な学びを支援する事業
イ 居場所の提供・相談支援を行う事業
ウ 衣食住など生活の支援を行う事業
エ 児童又はその保護者の就労を支援する事業
オ 児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業
カ その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
(上記アからカまでに示す事業は、子供の貧困対策に係る事業である必要があるが、 同時に、児童虐待や青少年育成における課題など、子供の貧困の背景に存在する様々な社会的要因の解消にも資する内容を伴う事業についても申請が可能。)
●支援対象期間:2023年4月1日から2024年3月31日までとします。
|
| 支援金額 |
上限金額300万円
|
| 申込期限 |
2022年9月20日(火)※15:00(応募フォーム登録完了)
|
| お問合せ |
独立行政法人福祉医療機構 NPOリソースセンター NPO支援課
|
| URL | https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5/ |
|
名称
|
2022年度 社会福祉事業 NPO基盤強化資金助成「組織および事業活動の強化資金助成」
|
|---|---|
| 内容 |
公益財団法人SOMPO福祉財団では、福祉および文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高齢者などを対象として活動するNPOの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成などを実施しています。
「NPO基盤強化資金助成」では、NPOの基盤強化となる「組織の強化」と「事業活動の強化」に必要な資金を助成します。
●対象となる団体:
下記の<1>~<3>のすべてを満たしている団体が対象です。
<1>募集地域
東日本地区(以下の都道府県)
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・
埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・ 福井県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
<2>助成対象者
特定非営利活動法人・社会福祉法人(インターネット申請が可能な団体)
<3>助成対象事業
社会福祉に関する活動を行う団体を対象とし、原則として2024年3月末までに完了する事業が対象です。
●助成内容:
・団体の基盤強化に結びつく事業に必要な費用
・組織の強化に必要な費用
・事業活動の強化のために行う、新規事業または既存事業の拡充・サービス向上に必要な費用
|
| 助成金額 |
1団体70万円(総額1,000万円予定)
|
| 募集期間 |
2022年9月1日(木)~10月7日(金)※17:00(インターネット申請のみ)
|
| お問合せ |
公益財団法人SOMPO福祉財団 事務局
|
| URL | https://www.sompo-wf.org/jyosei/kibankyouka.html |
|
名称
|
2022年度 社会福祉事業 NPO基盤強化資金助成「認定NPO法人取得資金助成」
|
|---|---|
| 内容 |
公益財団法人SOMPO福祉財団では、福祉および文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高齢者などを対象として活動するNPOの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成などを実施しています。
「NPO基盤強化資金助成」では、地域の中核となり、持続的に活動する質の高いNPO法人づくりを支援し、「認定NPO法人」の取得に必要な資金を助成します。
●対象となる団体:
社会福祉分野で活動し、認定NPO法人の取得を計画している特定非営利活動法人。
(インターネット申請が可能な団体)
※日本全国で募集します。
※以後「認定」という場合は、「特例認定」を含むこととします。
※なお、2022年4月1日以降に、認定NPO法人の取得申請をすでに提出している団体(認定済みの団体も含む)も対象です。
●助成内容:
「認定NPO法人」の取得に関する費用であれば、使途は問いません。
※会合費、人件費、器材費その他一切使途は問いません。
ただし、原則として2024年3月末までに所轄庁(都道府県・政令指定都市)に、「認定」の申請を行うことが必要です。
※所轄庁受付日が、2022年4月1日~2024年3月31日のものが対象です。 |
| 助成金額 |
1団体30万円(総額300万円予定)
|
| 募集期間 |
2022年9月1日(木)~10月7日(金)※17:00(インターネット申請のみ)
|
| お問合せ |
公益財団法人SOMPO福祉財団 事務局
|
| URL | https://www.sompo-wf.org/jyosei/nintei-npo.html |
| 名称 |
地域活動団体への助成「生活学校助成」
|
|---|---|
| 内容 |
近所のお年寄りや子どもたちの見守り、ごみの回収や資源リサイクル活動など、身近な地域や暮らしの問題に取り組むグループの皆さま、生活学校に参加してみませんか?
生活学校の趣旨に賛同し、参加を希望する地域活動団体の募集を行い、当協会から活動経費の助成を行います。
◆生活学校とは?
身近な地域や暮らしの様々な課題について、学び、調べ、話し合い、他のグループとも協力しながら、実践活動のなかで解決し、生活や地域や社会のあり方を変えていく、そんな活動に取り組むグループです。
これまで「食品表示の適正化」「休日・夜間診療の実現」「缶飲料のステイオンタブ化」「資源ごみの分別収集」などの取組みは、現在の私たちの生活に根付いた成果になっています。
また、全国の生活学校が連携して取り組む全国運動「食品ロス削減」「震災復興支援活動」「レジ袋削減」などは、内閣総理大臣賞をはじめ高い社会的評価も受けています。
現在は全国運動「食を通じた子どもの居場所づくり」に取り組み、全国の団体が連携した運動の展開を図っています。
●対象団体(①及び②の両方に該当する団体):
①身近な地域や暮らしの課題解決に取り組む地域活動団体
②全国の生活学校が連携して行う全国運動に参加する意向のある団体
●全国運動の活動実施時期:
全国運動の活動実施時期については、令和4年度中(令和5年3月末まで)のご都合の良い時に取り組んでいただければ結構です。
|
| 助成金額 |
①生活学校への参加 6万円(初年度3万円、2年目3万円)
②全国運動への参加 上限5万円(現在のテーマは「食を通じた子どもの居場所づくり」)
|
| 申込期限 |
2022年10月31日(月)
※メールでご連絡のうえ、申請書類をお取り寄せください。
|
| お問合せ |
公益財団法人あしたの日本を創る協会 生活学校募集係
|
| URL | http://www.ashita.or.jp/sg2.htm |
| 名称 |
2022年度(第5回)子ども支援活動助成
|
|---|---|
| 内容 |
●応募課題:子どもたちに夢と笑顔を、そして輝く未来につなぐ支援活動
<助成対象の活動例>
1.子どもの居場所づくり活動(環境改善)
2.子どもの学習支援活動
3.貧困家庭の子ども支援活動(貧困の連鎖の防止)
4.育児放棄や子どもの虐待防止活動
●応募資格:
20名以上で活動し、かつ営利を目的としない団体
(任意団体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等)。
※活動実績5年以上でかつ当財団を含め過去の助成実績(含む補助金)が2回以上ある団体に限ります。
※同時募集の「第29回ボランティア活動助成」との同時応募はできません。
※公的機関は助成の対象となります。
|
| 助成金額 |
上限50万円(1団体あたり)総額500万円
1団体あたり最大3年間 最大助成額(1団体あたり)150万円
※継続支援に際し、毎年、審査を実施いたします。審査は申請内容に応じ「進捗状況」や「新たな課題の発見」などによるものとします。
●対象期間:2023年4月1日(土)~2024年3月15日(金)
|
| 申込期限 |
2022年9月15日(木)※当日消印有効
|
| お問合せ |
公益財団法人大和証券福祉財団 事務局
|
| URL | https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html |
| 名称 |
2022年度(第29回)ボランティア活動助成
|
|---|---|
| 内容 |
●応募課題:
1.高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動
※2019年度以降(第26回~28回)の受贈団体は、応募資格がありません。
2.地震・豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支援活動
※大規模自然災害とは、「東日本大震災」「平成28年熊本地震」「平成29年7月九州北部豪雨」「大阪府北部地震」「平成30年7月豪雨」「北海道胆振東部地震」「令和元年台風15・19号10月25日からの大雨」「令和2年7月豪雨」等
●応募資格:
5名以上で活動し、かつ営利を目的としない団体
(任意団体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等)。
※活動実績は問いませんが、設立して間もない団体による応募は、助成対象期間の活動予定が決まっている団体に限ります。
※同時募集の「第5回子ども支援活動助成」との同時応募はできません。
※公的機関は助成の対象がとなします。
●対象期間:2023年1月1日(日)~12月31日(日)
|
| 助成金額 |
上限30万円(1団体あたり)総額4,500万円
|
| 申込期限 |
2022年9月15日(木)※当日消印有効
|
| お問合せ |
公益財団法人大和証券福祉財団 事務局
|
| URL | https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html |
| 名称 | 「ボラサポ・令和4年8月豪雨」助成(短期活動助成) |
|---|---|
| 内容 |
●対象団体:
令和4年8月豪雨により、令和4年8月3日から令和5年1月31日までに、災害ボランティアセンター等が設置された市町村において、被災された方々や地域に対する復旧のための支援活動を行う、ボランティアグループ、特定非営利活動法人(以下、NPO法人)、社会福祉法人、学校法人、公益法人、一般社団法人等であって、次の要件にあてはまる非営利団体(令和4年7月14日からの大雨災害により、宮城県内で令和4年7月14日以降に活動を行った団体も含む)
●助成対象期間:
・対象活動期間:令和4年8月3日から令和5年1月31日
(令和4年7月14日からの大雨災害により宮城県内で活動を行った場合は、対象期間を令和4年7月14日からとする)
・活動日数:上記期間のうち、30日以内の活動
本助成事業では、上記対象期間中に、令和4年8月豪雨により被災された方々を支援するため、災害ボランティアセンター等が設置された市町村において、応募団体が被災地にて直接行う活動を対象とし、既に終了した活動であってもさかのぼって応募することが可能です。(すでに終了している活動について応募する場合でも、応募団体を紹介した被災地の「自治体・社会福祉協議会等」の紹介者に対し、ヒアリングや必要書類の提供依頼等を行い、活動が行われていたことが確認できることを条件とします。)
また、応募にあたっては、令和4年9月20日以前に支援活動が開始されていることを条件とします。
対象となる活動内容は以下の通りです。
◆緊急救援、復旧支援活動
災害発生直後の混乱から、家屋等における復旧作業等の緊急的な支援活動が実施される時期に行われる活動
※原則として、発災直後から行われる緊急救援活動や復旧支援活動を対象とします。
※そのうえで、活動における新型コロナウイルス感染予防の衛生管理を行われていることを対象とします。具体的に行っている感染予防対策を応募書に記載ください
|
| 助成金額 | 1団体あたりの助成額:50万円以内 |
| 申込期限 | 令和4年8月16日(火)~令和4年8月29日(月)必着 |
| お問合せ |
社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部(ボラサポ担当)
|
| URL | https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/vorasapo/28672/ |
| 名称 | 女性リーダー支援基金 ~一粒の麦~ |
|---|---|
| 内容 |
「ジェンダーギャップ指数」において世界から大きく遅れをとっている日本では、女性のリーダーが育ちにくい状況にあります。こうした現状を変えていくため、次世代リーダーを目指す女性たちをサポートする「女性リーダー支援基金 ~一粒の麦~」第2回目の公募を開始しました。
初年度(2021年度)は、137名のご応募より審査委員会による厳正なる審査の結果、5名の支援対象者を決定し、1人100万円の活動奨励金を支給しました。本年度も支援対象者には100万円の活動奨励金が送られる他、交流会等による非資金的な支援を行います。
国政・地方を問わず政治家をめざすための講座・研修を受講した経験のある方、
大学・大学院等で社会課題 について学んでいる方、
社会活動(NPO・NGO・オンラインアクティビズム等)を実践されている方等を対象としています。
【支援対象分野】
①政治家志望者 ※既に公職の議員や首長となっている場合は除く
②社会活動(NPO・NGO・オンラインアクティビズム等)の実践者
③社会起業家志望者
④女性のためのアクションリサーチの企画・実践者
|
|
支援内容及び採択予定件数 |
1年間に5名、3年間で計15名程度を選定し、1人あたり100万円の活動奨励金を支給
<2022年度>
・活動奨励金: 1人あたり100万円 支援予定者数: 5名程度
・活動奨励金の他に、交流ミーティング、メンター制度等の非資金的サポートを実施します
(サポート内容は変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
|
| 募集期間 | 2022年7月20日(水)~8月22日(月)17:00まで |
| お問合せ | 公益財団法人パブリックリソース財団 女性リーダー支援基金事務局(担当:渡邉、松本) |
| URL |
https://www.public.or.jp/project/f0159
【基金に関する情報】
◎オンライン公募説明会(アーカイブ・配布資料有)・・・支援内容や応募方法について
https://www.youtube.com/watch?v=hq1meKa2d7k
|
| 名称 |
令和4年8月大雨被害に関わる支援活動
|
|---|---|
| 内容 |
今回の被害において支援活動を行うNPO法人やボランティア団体等に対して、その活動資金の支援を行います。
令和4年8月大雨の被災地支援においては、新型コロナウイルス感染が懸念されている状況にあり、本来の災害ボランティア等の支援活動は、個人個人の自由な意思に基づいた、自発的な活動であることが原則ですが、支援活動を行うことで感染を広めてしまう恐れがあります。被災地域は、人口に占める高齢者の割合も高く、感染の広がりが被災地の住民の命を脅かす事態もありうることを充分に認識して活動を行ってください。また、県及び被災市町村などの意向をふまえ、被災地の状況や情報をよく確認したうえで支援活動を行ってください。
●対象団体:
NPO法人等(ボランティア団体含む)非営利活動を行う団体で、次の項目に該当する団体
【被災県内に所在する団体】
新型コロナの状況を鑑み、被災県内に所在する団体に限ります。
(県外ボランティアの受入が開始された場合は、支援対象を拡大します)
※被災県は、山形県、新潟県、石川県、福井県、青森県、岩手県、秋田県、福島県、滋賀県等、支援ニーズが確認された自治体。(2022年8月6日時点)
●対象の事業:
2022被災地拠点の団体による被災地ニーズに沿った活動(土砂撤去、サロン活動等)
専門的な支援を行うNPO等の活動(重機等による水害復旧活動、看護福祉専門職・鍼灸マッサージ師等による活動)
特別なニーズ(障害者・高齢者・乳幼児・外国人などの要配慮者)に対する専門性を活かした活動(要配慮者の生活復旧支援等)
上記の活動において、申請日から3週間程度は活動が見込まれる事業
●活動対象期間:2022年8月3日(水)以降、団体が活動を開始した日から2023年3月31日(金)まで
|
| 助成金額 |
1事業あたり100万円を上限とする。
|
| 申込期限 |
第1期:2022年8月31日(水)まで(決定は審査の上、随時行います)
第2期:2022年9月23日(金)まで(決定は審査の上、随時行います)
|
| お問合せ |
公益財団法人日本財団 災害対策事業部(令和4年8月大雨)
メールアドレス:saigai@ps.nippon-foundation.or.jp
|
| URL | https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/r408disaster-npo |
| 名称 | 2022年 こくみん共済 coop〈全労済〉地域貢献助成 |
|---|---|
| 内容 |
防災・減災活動、環境保全活動、子どもの健全育成活動について、
地域で活動している市民団体等を支援いたします。
●助成の対象となる活動:
(1)自然災害に備え、いのちを守るための活動
(2)地域の自然環境・生態系を守る活動
(3)温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
(4)子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動
(5)困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動
●助成の対象となる団体:
日本国内を主たる活動の場とする、次の(1)~(3)のすべてに該当する団体を対象とします。
(1)NPO 法人、一般社団法人、任意団体、市民団体など
(2)設立1年以上の活動実績を有する団体 (基準日 2022年8月17日 ※応募受付開始日)
(3)直近の年間収入が300万円以下の団体(前年度の繰越金を除く)
●対象となる活動期間:
2023年1月1日~2023年12月31日の間に実施、完了する活動が対象です。
|
|
助成金額 |
助成総額:2,000万円(上限)予定
1団体に対する助成上限額:30万円
|
| 募集期間 | 2022年9月16日(金) |
| お問合せ |
こくみん共済 coop 〈全労済〉 地域貢献助成事業事務局
|
| URL | https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei |
いわて未来づくり機構(事務局:岩手県復興防災部復興推進課)様主催のイベントのご案内です。
令和4年度 第2回「いわて復興未来塾」の開催について
| 名称 |
2022年度 環境助成金プログラム
|
|---|---|
| 内容 |
私たちは、直接行動する課題を持った、草の根で活動する小規模なグループや、自然環境を保護/回復させようとする複数のキャンペーンに取り組んでいるようなグループを支援しています。
パタゴニアは株式を公開しておりませんので、株主に縛られることなく、通常の道からは多少外れているグループも支援することができます。また、私たちはそのような小さなグループを支援していくことが最も効果的だと信じています。
●助成対象:
・多様性、公平性、かつ包括性のある環境ムーブメントを構築している
・環境政策やアウトドアにおける体系的な偏見、差別、不公正に立ち向かうもの
・行動志向であること
・計測可能であること
・市民を巻き込み、支持を得ている
・ターゲットと目標において戦略的に活動している
・問題の根本的原因に焦点を当てている
・成功が効果的に測定できる特定のゴールとも目標を達成している
上記に加えて、タイズ財団が定める以下の条件を満たす必要があります。
・プロジェクトベースの申請であること ※通常の管理運営経費に対する助成は対象外となります。
・プロパガンダや特定の法律制定に影響を及ぼすことを意図したロビー活動の実施を目的とするプロジェクトではないこと
・アメリカ合衆国以外で実施されるプロジェクトであること
|
| 助成金額 |
50~200万円
※申請内容によってはこの範囲を超えて助成する場合があります。
|
| 申込期限 |
年2回(4月と8月)申請の締め切りを設けている環境助成金プログラムですが、
今年度の申請は2022年8月31日(水)のみとなります。
|
| お問合せ | パタゴニア日本支社 助成金プログラム窓口 |
| URL | https://www.patagonia.jp/how-we-fund/ |
7月6日(水)、山田町社会福祉協議会にて今年度1回目となる「わくわくやまだ座談会」を開催しました。
「わくわくやまだ座談会」では、山田町社会福祉協議会といわて連携復興センターが事務局を担当し、山田町で活動している団体と山田町役場、山田町社会福祉協議会が互いの活動紹介や地域課題に関する情報交換会を行っています。
これまで新型コロナウイルス感染拡大の影響で、しばらくオンライン開催が続いておりましたが、県内の感染状況も考慮しつつ、タイミングを見計らって、久しぶりにリアルに開催することができました!
情報交換会では、各団体の活動紹介や近況報告の他、「子ども」をテーマに議論が行われ、今後の連携のきっかけとなるような情報交換が行われました。
7月29日(金)、やまだわんぴぃすが主催する「行ぐべす畑さ!」の畑づくりに参加しました。
「やまだわんぴぃす」は東日本大震災以降、山田町を中心に自然の中に遊び場と畑が混在する「居場所」を作り、地域コミュニティの復興を目指す取り組みを行っています。
「行ぐべす畑さ!」では、畑仕事の体験会を実施して、地域の世代間交流を図るとともに、畑仕事を通じて食べ物を作る喜びの発見、地域の人たちとの繋がりを経験することにより、生きがいをつくることを目的としています。
今回は山田町の災害公営住宅・山田中央団地付近にある土地をお借りして、団地入居者と山田高校の高校生ボランティアが一緒に種蒔き作業、看板づくりを行いました。
今後も畑づくりを継続して実施するほか、長崎街道沿いにお花の植栽、野菜の収穫体験なども予定されています。お近くにお住まいの方、山田町に寄られた方はぜひ足を運んでみてください!
岩手県内や日本各地で大雨被害により、
被災された多くの皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
8月3日からの大雨被害については、弊団体が事務局を担っております
「いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)」として、
岩手県内を中心に被災状況の確認と支援活動に動いております。
一日も早い復旧をお祈りするとともに、
被災された皆様が平穏な日々を取り戻せるようお祈り申し上げます。
■いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)ホームページ
https://iwate-inds.jp/
■いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)Facebook ※日々の活動発信
https://www.facebook.com/iwateinds
岩手県内では、一戸町と九戸村で災害ボランティアセンターが設置されています。
新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、ボランティア募集地域を確認しながら、
是非、活動にご協力をお願いします。
また、ボランティア活動以外にも、情報の拡散や寄付等で支援する方法もあります。
これからお盆を迎える被災地へ、是非あたたかいご支援を宜しくお願い致します。
■一戸町災害ボランティアセンター
https://ichinohe-shakyo.jp/pages/26/
*新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ボランティア募集は主に二戸圏域在住の方のみに
限らせていただきます。また、応募の際には、ワクチン接種(3回以上)証明書または、
抗原検査の陰性証明書の提示をお願いいたします。
■九戸村災害ボランティアセンター
http://www.kunohe-shakyo.jp/cgi-bin/data_of_news.cgi?type=v&f1=1659927087
*新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ボランティア募集は九戸村内に在住の方のみに
限らせていただきます。
| 名称 |
ウクライナ避難民支援 助成プログラム
|
|---|---|
| 内容 |
本助成プログラムは、各地域におけるウクライナ避難民の受け入れ態勢の整備を目的に、ウクライナ避難民の受け入れや生活支援を行う各地域の市民社会の活動や、それらの支援活動の連携をコーディネートする事業等を対象に助成を行うものです。
●対象団体:
日本国内にて次の法人格を取得している団体:一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人(国立大学法人を含む)、任意団体(法人格のない団体)など非営利活動・公益事業を行う団体
●対象となる事業:
国内の各地域においてウクライナからの避難民に対して生活支援を提供する事業や、自治体や他支援団体と連携しながら地域の支援をコーディネートする事業。
避難民の日々の生活に必要とされる生活支援を各受入れ地域で提供することや、受け入れから生活支援までを一貫して提供できる態勢や各種生活支援を一体的に提供できる態勢の構築を目的とします。
<想定する事業例>
・衣食住の保障に関する相談、支援事業
・子どもへの学びの機会提供や、居場所づくりの事業
・日本での就労に向けた準備、研修事業(日本語学習など)
・メンタルヘルスのケア、心理的サポートを提供する相談、支援事業
・女性特有の課題に関する相談、支援事業
・避難民と地域社会(自治体、学校、医療機関、介護施設など)を相談員が結び、伴走する事業
・地域住民との交流の場を提供し、地域における共生を促進する事業
・教育機関等と連携し避難民の受入れと教育支援を行うコーディネーション事業
・企業等と連携し避難民の受入れと就労支援を行うコーディネーション事業
・自治体や各支援団体間の連携による生活、教育、就労等の一体的な支援事業
・上記のような事業を行う事業者のプラットフォームとして情報共有・発信を行う事業
●事業期間:助成契約締結日以降、2023年3月末日まで
|
| 助成金額 |
上限:300万円 ※任意団体は100万円上限
補助率:100%
|
| 申込期限 |
2022年12月31日(土)※17:00まで
|
| お問合せ |
公益財団法人日本財団 ウクライナ支援 問合せ
|
| URL | https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/support_ukraine |